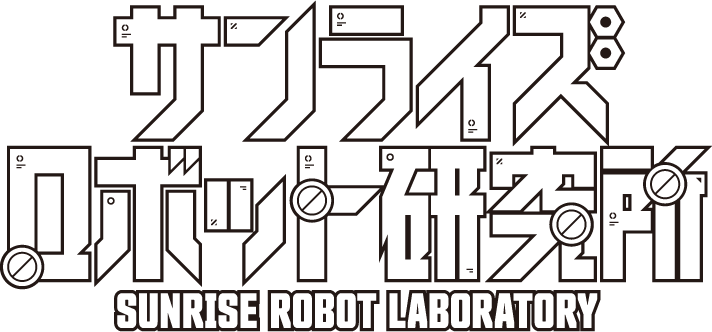第2回「生体力 ―― 人の業とマインドの輪廻」 (『聖戦士ダンバイン』より)
「バイストン・ウェルの物語を覚えている者は幸せである。私たちは、その記憶を記されてこの地上に生まれてきたにもかかわらず、思い出す事の出来ない性(さが)を持たされたからだ」。これはバイストン・ウェルを表現する際に引用されてきた名文句で、特に書き出しなどは詩的な美しさをもって読む者の想像力を刺激する。

はたして、人々は魂の根っこ、奥底にバイストン・ウェルの刷り込みがあるからこそ、ミ・フェラリオを見ても妖精のようだと腑に落ちるし、チ・フェラリオ、エ・フェラリオを見て天女や女神を想起し、ガロウ・ランを悪魔や妖怪のごとく意識するし、深層に棲まうカ・オスの存在は知り得ないまでも、悪の根源的存在として感じ、恐怖するのである。
それらバイストン・ウェル特有の存在については後に触れるとして、いまは冒頭の一節に戻ろう。「バイストン・ウェルの物語を覚えている者は幸せである」――だが……ひとりの例外もなく、胎内から外の現実へと生まれ出た瞬間、その記憶を思い出せなくなってしまうのに。バイストン・ウェルでの魂の浮遊を覚えている者など、どこに居るというのか? 居はしないのだ。
そう、かの一節が言外に語っていることは、「あり得ない」のではないか? であれば、そのような幸福は地上にないことを示していることになる。しかるに、地上は魂にとって試練の場。バイストン・ウェルから放たれゆく現実(リアル)は地獄 なのだから、心せよ――と。
バイストン・ウェルに在る者たちが述べる通り、そこが「人の魂の安息の世界」だとしよう。対して、地上はどうか。そこで人は魂の宿る肉体、物理的な存在として生き、知と情を交わし、高め、磨く――削り合う。物理的には命の連鎖を目的としつつ、肉体の修練(経験)によって精神という気を通じる脈、気脈を強化し、自らの意思もつなげようとする。人類という枠で見ればおびただしい数の熾烈な争いを、あらゆる時代で繰り返しながら、いつしか魂は疲れ切り、肉体から去る。去ってどこへ向かうのか。
死したのち、人はどこへ行くのか。古今東西を問わず、人類が求め続けたその先にある場所こそ、「人の魂の安息の地」――バイストン・ウェルである。そこで、魂は自らを慰撫する。肉体から解き放たれ、自堕落に、魂はバイストン・ウェルで遊ぶ。そうした魂を迎え入れ、内包することでバイストン・ウェルという≪界≫は魂の力=オーラ・エナジィというべきものを蓄積し、息づく。この関係性から、魂はバイストン・ウェルの細胞として例えられている。
仮に、我々地上人の感性でかの世界を定義するならば、「オーラ・ワールド」 と称することが出来よう。そこは人類が知りたいと求め続けた「生死の前後に在る場所」であり、還るべき、また、その安寧から脱し、肉体を具備した生を迎えるための準備をする場所なのだ。
こうしてバイストン・ウェルに遊ぶ魂は世界を支える力=オーラ・エナジィを高め、バイストン・ウェルは自己拡大を続けていく。遊び心多きフェラリオにせよ、邪欲を隠さぬガロウ・ランにせよ、その他の大多数が無意識に望む人らしさを示すコモン人としてにせよ――バイストン・ウェルにおいて慰撫されたそれらの魂=エナジィは再び肉体と精神の修練の地上世界へと生まれ出ていく。この繰り返しは「輪廻」、生まれ変わりと人々が称してきたもの(reincarnation)にあたるかもしれない。
そのような人の魂との関係性から翻ると、バイストン・ウェルは、≪肉の界≫に生きる地上人の魂が「安息の地」を求めたことから発現した≪魂の界≫とする解釈も成り立つ。あるいは、バイストン・ウェルという存在が、オーラ・ロードを通じて人の魂を地上と輪廻させ、その循環のなかでエナジィを高めていく機構を育んだともいえよう。それは、オーラ・エナジィをもって自己という世界=バイストン・ウェルがフィールドを拡大するため、強固にするためである。この解釈を採るとき、バイストン・ウェルというものは、膨張し続ける宇宙の在り方に近いといえるだろう。