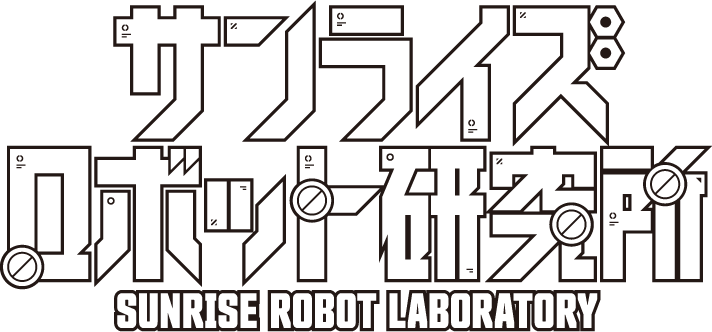第8回「聖戦士と、ドレイクの野望と」(『聖戦士ダンバイン』より)
諸国が相争う戦乱の続いてきたコモン界の統一。ショット・ウェポンがオーラ・バトラーの開発に成功してからというもの、アの国の一領主にすぎなかったドレイク・ルフトにとって、それは「夢」ではなく、当然果たすべき現実的な野望となった。しかし、愚王といえども主君に弓引き、また、諸国への侵略行為を正当化するためには、それなりの理由が必要であった。そのために、「聖戦士」の伝説は都合がよかったのである。自らの元に、地上から「聖戦士」が集う。それはドレイクにコモン界の乱れを鎮めよという、バイストン・ウェルの意思のあらわれであろう、と。
バイストン・ウェルに暮らすコモンの人々と鑑みて、地上人はこのオーラ力にすぐれているというのが、ドレイク・ルフトやショット・ウェポンが当初描いた絵であった。ことに、オーラ力が出力、戦闘力に直接影響するオーラ・マシンによる野望を企図するにおいて、オーラ・マシンを揃えると同時に、搭乗者としての地上人を是が非でも戦列に加えたいと考えた。そしてシルキー・マウにオーラ・ロードを開かせ、わかっているだけでもトッド・ギネス、トカマク・ロブスキー、ショウ・ザマ、アレン・ブレディ、ジェリル・クチビ、フェイ・チェンカらをオーラ・バトラーの搭乗者候補として召喚、彼らを「聖戦士」と持ち上げて自陣営に取り込んだのだ。オーラ・バトラーを製造できても、その真価を発揮するには相応のオーラ力の持ち主とセットでなければ意味がない――そう考えられたからこそ、ドレイクをはじめ各陣営は地上人をそのパイロットに迎えようとしたのだった。
オーラ・マシンが戦いの主役になるにあたって、地上人召喚を講じたのはドレイク・ルフトだけではなかった。その代表がギブン家で、隣領であるルフト家の動向を知ると、エ・フェラリオ(ナックル・ビー)の協力を得て地上人マーベル・フローズンを召喚、オーラ・バトラー「ダーナ・オシー」の搭乗者に迎えているのである。これはショウ・ザマ、トッド、トカマクの3名がバイストン・ウェルに登場するよりも前のことで、情報戦ではドレイク一派の一歩先を行っていたとさえいえる。
これら地上人たちは確かにコモン界の人々よりも――ドレイク軍の戦闘隊長バーン・バニングスよりも――強いオーラ力を示し、オーラ・バトラーをやすやすと操縦してみせたが、我が強く個性的なパーソナリティばかりで、反発や離反も数々招いた。内心、業を煮やすこともあっただろう。だが、一部の例外を除いてオーラ力の弱いコモン人ではオーラ・バトラーを満足に稼働出来ないという問題は、新型のオーラ増幅器(コンバーター)の開発によって解決される。これによってガラリア・ニャムヒーやポーの一族ら、ドレイク麾下での栄達欲や忠誠を示すコモン人も積極的にオーラ・マシンの搭乗者に取り立てられるようになった。そうすると、地上人が「オーラ力による特権」を認められる向きも弱くなり、純粋に戦果を求められることにも繋がっていった。
また、オーラ・コンバーターの改良、オーラ・バトラーの開発・生産と並行して、この時期に各国が力を注いだのが飛行艦船「オーラ・シップ」の建造であった。従来もオーラ・ボム、ウィング・キャリバーという飛行マシンの母艦となり、前線を移動する攻撃要塞のような役割を担うものであった。「ナムワン」「ブルベガー」、「ゼラーナ」さらには、疑似オーラ発生器の開発によって超長時間の飛行・航行が可能となった超大型のオーラ・バトルシップ――アの国・ドレイク軍の「ウィル・ウィプス」、ラウの国の「ゴラオン」、クの国の「ゲア・ガリング」、ナの国の「グラン・ガラン」が続々と戦線に姿を現し、各陣営が拠点を地から空へ移しはじめると、戦乱の拡大はもはや止められないものとなった。
こうして、それぞれの陣営がオーラ・バトラーやオーラ・バトルシップを開発し、その数が戦場を支配するようになっていくと、ただ大戦力を擁して優位な側が勝つ――オーラ・バトラー登場以前の戦いと大勢は変わらなくなっていく。そして、ドレイク・ルフト率いるアの国とビショット・ハッタのクの国の連合勢力が、ナの国以西をほぼ掌握するに至る。だが、そんな状勢下でも、ドレイクたちが無視できない存在があった。かつて地上より召喚され、一度はオーラ力の暴走で地上へ浮上したにもかかわらず、自らバイストン・ウェルへ舞い戻った、底知れないオーラ力の持ち主。オーラ・バトラー「ダンバイン」の搭乗者――「聖戦士」ショウ・ザマである。
戦乱の続いてきたコモン界の統一。長く愚王を戴いてきたアの国の行く末を案じるドレイク・ルフトにとって、それは「野望」ではなく、当然果たすべき大義であった。奇しくも、ダンバインはそのための旗機になるべく開発され、その名はルフト家の守護者という意味を持つ。それが、ドレイクの最大の壁として、あるいは、真の意味でルフト家が冒そうとする大罪への道を戒めるかのように存在を示したということに、皮肉めいた運命を感じずにはいられない。