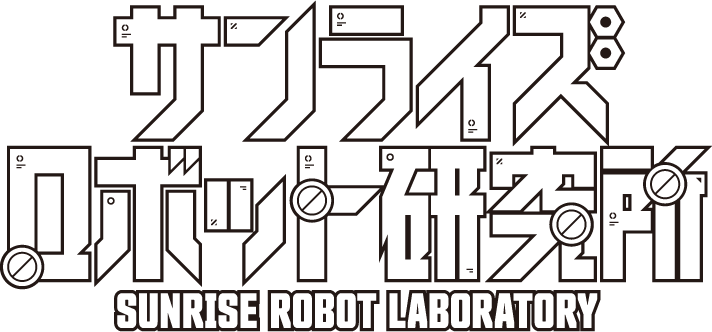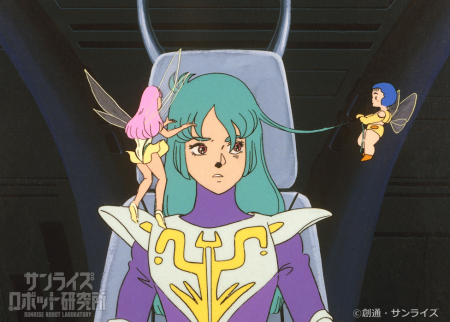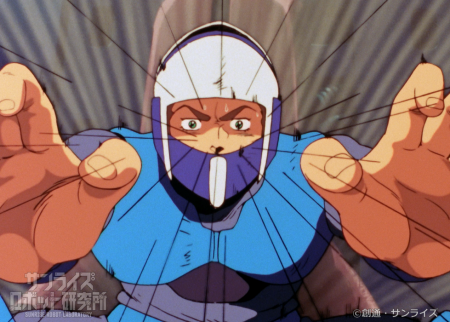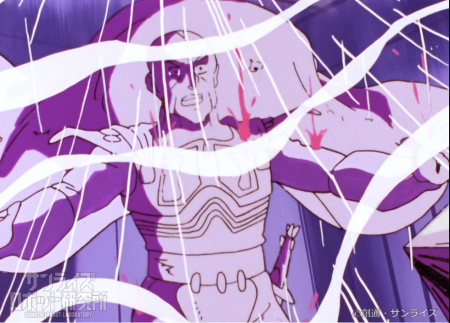指南講座
2024.08.09
第13回「大義の矛先――ドレイク・ルフトとニー・ギブン」(『聖戦士ダンバイン』より)
「バイストン・ウェルの機械は、地上世界を混乱に陥れています。私たちの手で、全てを終わらせなければならないのです」[シーラ・ラパーナ/太平洋上、グラン・ガラン艦橋にて]
「聖戦士」ショウ・ザマの物語は、異世界バイストン・ウェルの紛争に巻き込まれた地上人の顛末と見ることもできる。そこではアの国の王位をめぐる陰謀があり、地上の「機械」の技術が持ち込まれ、「オーラ・マシン」の開発競争が起こっていた。既に「戦い」は始まっていたのだ。その主要な人物たち、彼ら、彼女らが戦う理由を紐解けば、大乱の奥底にある何かに気付けるのではないだろうか。バイストン・ウェルと地上に破壊をまき散らした動乱の端緒と結末を眺望し、その背景を整理したい。
▼大義の矛先――ドレイク・ルフトとニー・ギブン
「海と陸の間の世界」バイストン・ウェルは深く、広大である。そのコモン界において「聖戦士」ショウ・ザマの戦跡はレンの海周辺の一地域に過ぎない。より詳細に語るなら、レンの海の西側諸国、特にレンの海に面すラウの国、ミの国、アの国と、アの国の西に隣接するクの国の動乱に巻き込まれたものであった。
戦火の端緒として先ず考察すべきは、ショット・ウェポンを召喚し、オーラ・マシンの開発への先鞭をつけたルフト家――アの国の地方領主、ドレイク・ルフトを挙げるべきであろう。
ドレイクは妻ルーザに、こう語ったという。「私の夢は、バイストン・ウェルそのものを手に入れる事だ。そのためには金も要るし、軍を動かす大義も要るのだ」。
多少の方便が含まれているにせよ、ドレイク・ルフトがオーラ・マシンの威力を背景にしてアの国と周辺を平定しようとしていたことは確かだ。「この百年、バイストン・ウェルそのものの倫理が崩れて、ガロウ・ランまでが暗躍する時代」とクの国王ビショットがもらしているように、少なくともレンの海周辺諸国では紛争と暴力の時代が訪れていたわけである。各国の間、あるいはその国内で武力の衝突が起き、混迷の時代になっていたことは明らかであろう。
そこにショット・ウェポンやゼット・ライトが現れ、「聖戦士」たちがこぞってドレイク・ルフトの元に集まるという状況は、自らの野望にバイストン・ウェルの意思がこたえたものと標榜するにふさわしかった。
そうして、着々と地盤固めをしていたドレイクはギブン家を反逆者に仕立て上げ、軍を動かす大義を得ると、その矛先をアの国王フラオンの居城・エルフ城に向けた。享楽にふけり、ドレイクこそ国の忠臣と刷り込まれてきたフラオン王には、ニー・ギブンたちゼラーナ隊の忠告も焼け石に水であった。アの国を掌中におさめたドレイクは、西のクの国との同盟を保険に戦線を拡大、ミの国、ラウの国を制圧にかかる――。その大きな野望がジャコバ・アオンやエレ・ハンムのいう「悪意」を集わせ、すべてのオーラ・マシンが地上へ放逐される「浮上」の一因となったことは間違いない。
そんなドレイク・ルフトの野望に敢然と立ち向かった、ニー・ギブンの戦う理由とは何であったか。当初は王家への反逆の意思を隠そうとしないドレイクの動向に対する理屈からであったが、ギブン家の館がバーン隊に焼き討ちされて母カーロを失い、その後に父ロムンもミの国への内通を計画していた反逆者との汚名を着せられると、その後はドレイク・ルフトへの仇討ちに執心していき、それを「個人の感情で戦っているんじゃないのか」とショウ・ザマから疑問視されることもあった。だが、それはバイストン・ウェルにおいては祖国や人間関係を持たず、特別に戦う理由のなかったショウも同じことである。個人の判断、思考――感情でもあるだろうそれらに基づいて、マーベル・フローズンに付いていこうとか、ドレイク・ルフトやバーン・バニングスのやり方を嫌っての行動も、やはり私情ではあっただろう。
ただし、ショウの指摘にも一理ある。ニー・ギブンはドレイクの娘リムル・ルフトと恋仲であったから、彼女との関係を成就しようというきわめて個人的な側面からも、ドレイク・ルフトは「相容れぬ敵」であったのだから。とはいえ――突き詰めれば、特にバイストン・ウェルにおける争いや戦いとは、そういう心のはたらきと無関係ではないかもしれなかった。大義を掲げ、自分たちこそが善である、正義の戦いであるのだと示す――だが、それは一面だけの問題であって、善意からであろうと、悪意からであろうと、戦う上では勝つか負けるかという結果しかない。負ければ蹂躙される。そうされたくないから、戦う力が必要である。戦う力を持てば、それを振るいたくなる――。その点において、ドレイク・ルフトの周辺国を平定するという大義も、ニー・ギブンの主君への忠誠、親の仇を討つという使命も、結局は個人の思惑に過ぎない。そして、そうした精神の――魂の発露が自由闊達に示されることこそ、コモン界の本来の姿であろうし、バイストン・ウェルという世界が望むところでもあったはずだ。
ニー・ギブンに話を戻すと、一時はリムルの救出と保護に固執することもあったが、結果としては、彼はゼラーナ隊の隊長として戦い抜く覚悟をした。そして、文字通りに全てを賭けた決戦で、ニー・ギブンはドレイク・ルフトの物語の幕を閉じることに成功する。血気にはやるだけで取るに足らぬ、ギブン家の小倅(こせがれ)が、自身の最期の局面に戦士として立ちはだかった時、ドレイクはどのような心境であっただろう。
「貴様に討たれるとはな」。バイストン・ウェルから放逐されてなお、地上に覇を唱えようとした野心の果てに。それは自嘲の呻きとも、戦士となった男への称賛とも聞こえるのだった。